☆ 生クリームのムムムッ! ≪初出『ポプコム』'90.12月号≫
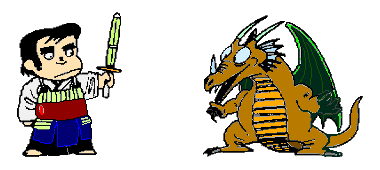
生クリーム……。いかに好きずきとはいえ、あまり嫌いという人は見かけない。ケーキだって、生クリームの多いほうがおいしいし、生シューの皮は生クリームを包装するためにある。アァ、生クリームをバケツ一杯くらい思いっきり食べてみたい!
匿名希望の貧田無一(ひんだ・むいち:21歳)は、友人のケーキ屋の息子サトシに向かって、そんな話をしていた。
二人とも地方出身の貧乏学生だが、皮下脂肪が限りなくゼロに近い無一に対して、さすがにケーキ屋の息子のサトシは小型ブッチャー(むろんアブドーラ・ザ・ブッチャーのことである)のような体型をしていた。しかも、さして生クリームに興味を示さないところが無一にはうらやましかった。
ある日、そのサトシが「小型冷蔵庫を実家まで運んでくれれば生クリームを好きなだけ食べさせる!」と無一に声をかけてきた。チャンス到来ッ!
早速、愛車スバル360(←昔はたくさん走っていた)で荷物を運んだ。そして、店も閉まった深夜に1リットルの生クリームを交代でホイップする。
悪戦苦闘の末に、大きなボウル2杯にタップリの生クリームが出来上がった。その瞬間は、棒のようになった右手の疲れを吹き飛ばすだけの魅力があったし、夢のような光景でもあった。だが……。
大さじ3杯。おいしいのは、そこまでだった。食べても食べても減らない生クリームの山は、見るだけでゲップを誘発し始めた。
しかし、こんなチャンスは二度とない。食べて食べて食べまくり、残りはタッパーに入れて持ち帰ることにした。すでに甘さで胸は焼け、口の中はバニラの香りもしつこくヌルヌル。もう見るのもイヤ!
それから二日後。少なくなった食べ残しのおいしいこと。改めて味わう、甘くとろけるような舌ざわり。これぞ憧れの生クリーム。
ウ〜ム、また山のように食べてみたい。そう思う気持ちと裏腹に、ふと「過ぎたるは及ばざるが如し」という秀逸なことわざが、胸のあたりから自然発生的に込み上げてきたのであった。ウ〜ップ……。
≪時は流れて……2004年1月≫
すでに生クリームは憧れの対象ではないし、どこの家庭でも簡単に作れる存在となってしまった。それだけに、さすがに当時と同じ気持ちを抱くことはない。
これを幸せと思うべきなのか、それともあの程度で幸せを感じられるほうが幸せだったのか、いくら考えても正解は出てこない。もしかすると、人生とは「正解のないものに対して正解を求め続ける旅」なのかもしれない。